2025年4月から放送中のNHKドラマ『しあわせは食べて寝て待て』は、団地での静かな生活と薬膳を取り入れた食事を通じて、主人公が心と体を回復させていく物語です。
ドラマ内で重要なテーマとなる「薬膳」は、どのような意図で取り入れられているのでしょうか?そして、その薬膳は誰が監修しているのかも気になるところです。
本記事では、『しあわせは食べて寝て待て』における薬膳の役割や監修者の背景、登場する料理の意味などを深掘りしてご紹介します。
この記事を読むとわかること
- NHKドラマの薬膳監修者・鈴木養平氏の役割
- 薬膳がドラマのテーマに選ばれた理由と意味
- 家庭でも実践できる薬膳の工夫や効果
『しあわせは食べて寝て待て』の薬膳監修者は誰?
2025年4月スタートのNHKドラマ『しあわせは食べて寝て待て』は、団地暮らしを通して薬膳と出会い、心身を整えるというテーマが大きな魅力となっています。
ドラマで登場する数々の薬膳料理は、薬日本堂漢方スクールの鈴木養平講師によって監修されています。
鈴木講師は中医学の専門知識に基づき、季節や登場人物の体調、心情に合わせた薬膳レシピの提案を行っており、ドラマの「食」に深みと説得力を与えています。
薬膳とは、東洋医学の理論を基盤とした食事療法であり、単に栄養を摂るだけでなく、五臓六腑の働きを整え、自然治癒力を高めることを目的としています。
そのため、さとこの体調や心の動きに呼応する薬膳メニューの演出は、物語の重要な要素として視聴者の共感を呼んでいます。
一見地味な料理にも見える薬膳ですが、「しあわせは、食べて寝て待てば訪れる」という本作のメッセージを体現する象徴的な役割を果たしています。
鈴木講師の監修により、使用される食材や調理法には説得力があり、家庭でも再現できる薬膳メニューとしても注目されています。
なぜ薬膳がドラマの軸になったのか
ドラマ『しあわせは食べて寝て待て』では、主人公・麦巻さとこが生活の激変に直面しながら、自分を取り戻すきっかけとして「薬膳」を生活に取り入れることが描かれています。
この物語の構成において、薬膳が中心的なテーマになった理由には、薬膳の持つ「体と心を整える」という東洋的な哲学が大きく関係しています。
食材ひとつひとつに意味があり、季節や体質に合わせて調和を図るという考え方は、現代社会に生きる人々のストレスや不安へのやさしい処方箋となるからです。
さとこは、病をきっかけに仕事や住まいを失い、人生の再構築を余儀なくされます。
その中で出会った団地の住人たち、特に訳ありの料理人と薬膳との出会いによって、彼女の暮らしは静かに、しかし確かに変化していきます。
薬膳という静かな営みが、さとこの心の揺れや回復のプロセスを丁寧に映し出すための媒体として機能しているのです。
また、現代の視聴者にとっても、「食を通じて整える暮らし方」は共感性が高く、健康志向やスローライフといった価値観にも通じるテーマです。

華やかではないけれど、じんわりと温かくなるような生き方が癒されるな
ドラマに登場する薬膳メニューの効能とは
『しあわせは食べて寝て待て』の中で、さとこが口にする薬膳料理は、見た目には素朴ながらも体を芯から整える力を持つメニューばかりです。
特に印象的なのが、ドラマの序盤に登場する「お粥」や「旬の野菜を使った煮物」など、消化にやさしく栄養価の高い料理の数々です。
これらのメニューは、中医学でいう「気・血・水」の巡りを整え、内臓の働きを高める効果があるとされ、まさに病後や疲労時に最適な食事です。
たとえば、朝食として登場する薬膳粥には、陳皮(ちんぴ)や棗(なつめ)などの生薬が使われており、胃腸を温めて気の巡りを良くする効能があります。
また、旬の野菜を中心に使うことで、自然と調和した食事スタイルを提案しており、体の負担を最小限に抑えながら必要な栄養を摂取できます。
これらの献立は、さとこが団地で暮らし始める中で少しずつ自分を取り戻していく過程を、視覚的にも温かく演出しています。
薬膳料理には、「食べて治す」「食べて癒す」という哲学が根付いています。
この考え方が、日々の暮らしの中で揺らぎやすい心身を優しく包み込むような安心感をもたらしてくれるのです。

真似したくなる薬膳の数々に、食の力の大きさを改めて感じちゃう
実生活でも真似できる薬膳の工夫
『しあわせは食べて寝て待て』に登場する薬膳メニューは、専門的すぎず、誰でも家庭で実践できる内容になっている点も大きな魅力です。
ドラマの中では、特別な調理器具や高価な食材はほとんど登場せず、スーパーで手に入る旬の野菜や乾物、薬膳素材がさりげなく使われています。
たとえば、生姜や長ねぎ、にんじんなどの食材は、身体を温め、気の巡りを助ける代表的な薬膳食材です。
さらに、季節の変わり目には「潤す」食材として、白きくらげや梨、はちみつなどが登場し、乾燥による不調に配慮したメニュー構成がなされています。
このように、薬膳は難解な知識がなくても「今の自分の体調に合った食材を選ぶ」ことで始められるのです。
さとこのように、生活の中で少しずつ薬膳を取り入れていく姿は、多くの視聴者にとって現実的で共感しやすいアプローチとなっています。
また、ドラマ内では、簡単な薬膳レシピの紹介や、団地の住人たちの料理アドバイスなども盛り込まれており、視聴しながら「今日の夕飯に真似してみようかな」と思えるシーンが多数あります。
薬膳を生活に取り入れることで、食べることが自分を大切にする行為へと変わっていくという実感が得られるのも本作の大きな特徴です。

「特別なことをしなくても、毎日のごはんが体を整える時間になる」——そんな気づきを与えてくれるヒントが詰まってるよね
薬膳と登場人物の関係性
ドラマ『しあわせは食べて寝て待て』の主人公・麦巻さとこは、「一生つきあわなくてはならない病気」によって、それまでの生活をすべて失います。
会社を辞め、安価な団地へ引っ越し、新たな環境で再出発を余儀なくされたさとこが出会ったのが、薬膳という“心と体を癒す食事”でした。
最初は戸惑いながらも、薬膳料理を通じて少しずつ自分を大切にする感覚を取り戻していきます。
薬膳を作ること、そして食べることは、彼女にとって「生きる実感」を取り戻す儀式のようなものでした。
体調に合わせたお粥を丁寧に作ることで、不安に揺れる心を落ち着け、未来に対して前向きな気持ちを持つようになっていきます。
また、体調が整ってくることで、人との関わり方も柔らかくなり、団地の人々との関係性も次第に豊かになっていきます。
この変化は、「食が人を変える」というテーマをドラマの中で丁寧に描いた作品です。
毎日の薬膳料理が、単なる健康管理を超えて、“自分と向き合う時間”を作り出していたのです。

薬膳を通じて描かれる人間関係の温かさ
『しあわせは食べて寝て待て』の中で薬膳は、さとこの心身を癒すだけでなく、人と人をつなぐ「媒介」としての役割を果たしています。
団地の隣人・鈴や司、そして他の住人たちとの絆は、一緒にご飯を囲む時間や、薬膳料理のやりとりを通して深まっていきます。
薬膳料理を振る舞うことは、「あなたのことを気にかけている」という無言のメッセージでもあり、それが彼女たちの心を開かせるきっかけになっているのです。
特に印象的なのは、司が心を閉ざしていた頃、さとこが薬膳をきっかけにそっと距離を縮めていく描写です。
言葉がなくても、食事を共にすることで通じ合える——このドラマはそんな「食の力」を静かに語りかけてきます。
「一緒に食べる」ことの価値や、「誰かのために作る」喜びが、自然とドラマの中に息づいています。
薬膳は決して豪華な料理ではないけれど、心に寄り添う温もりがある——だからこそ、それを通して生まれる人間関係は、どこか懐かしく、優しいものになるのです。
『しあわせは食べて寝て待て』薬膳と監修者情報のまとめ
NHKドラマ『しあわせは食べて寝て待て』は、静かな団地での暮らしを通して、薬膳という食の力で心と体を立て直していく物語です。
その中で重要な役割を果たす薬膳シーンは、薬日本堂漢方スクールの鈴木養平講師による専門的な監修のもとで制作されています。
リアルで実践的な薬膳メニューは、視聴者にとっても「真似したくなる、暮らしに取り入れたくなる」魅力を持っています。
さとこの薬膳との出会いは、単なる健康改善にとどまらず、人間関係や自己肯定感の回復にもつながっていきました。
そしてそれは、視聴者自身が「自分にもできるかもしれない」と感じる小さな希望にもなっています。
薬膳というテーマを丁寧に描いた本作は、“食べることは生きること”という原点を思い出させてくれるドラマとして、多くの支持を集めています。
今後の放送回では、どのような薬膳メニューが登場し、どんなエピソードと結びついていくのかも楽しみのひとつです。

食べることを通して、自分をいたわる。そのヒントが、ここにはきっとあります
この記事のまとめ
- 薬膳監修は鈴木養平講師(薬日本堂)
- 薬膳が主人公の心身回復のカギに
- 家庭でも再現可能な薬膳メニュー
- 登場人物の絆を深める“食”の演出
- 薬膳が伝える「食べて整える暮らし」
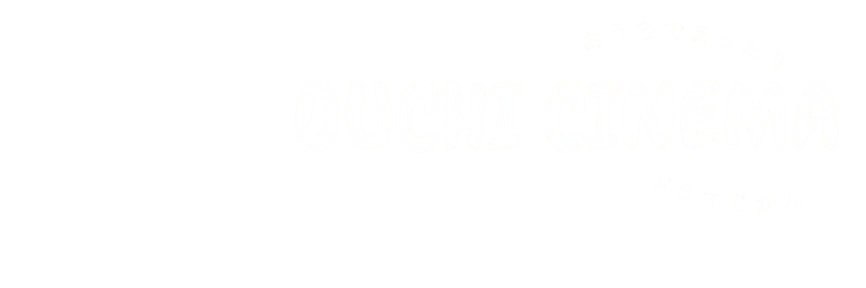


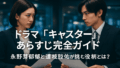
コメント